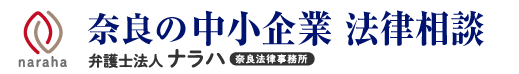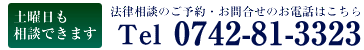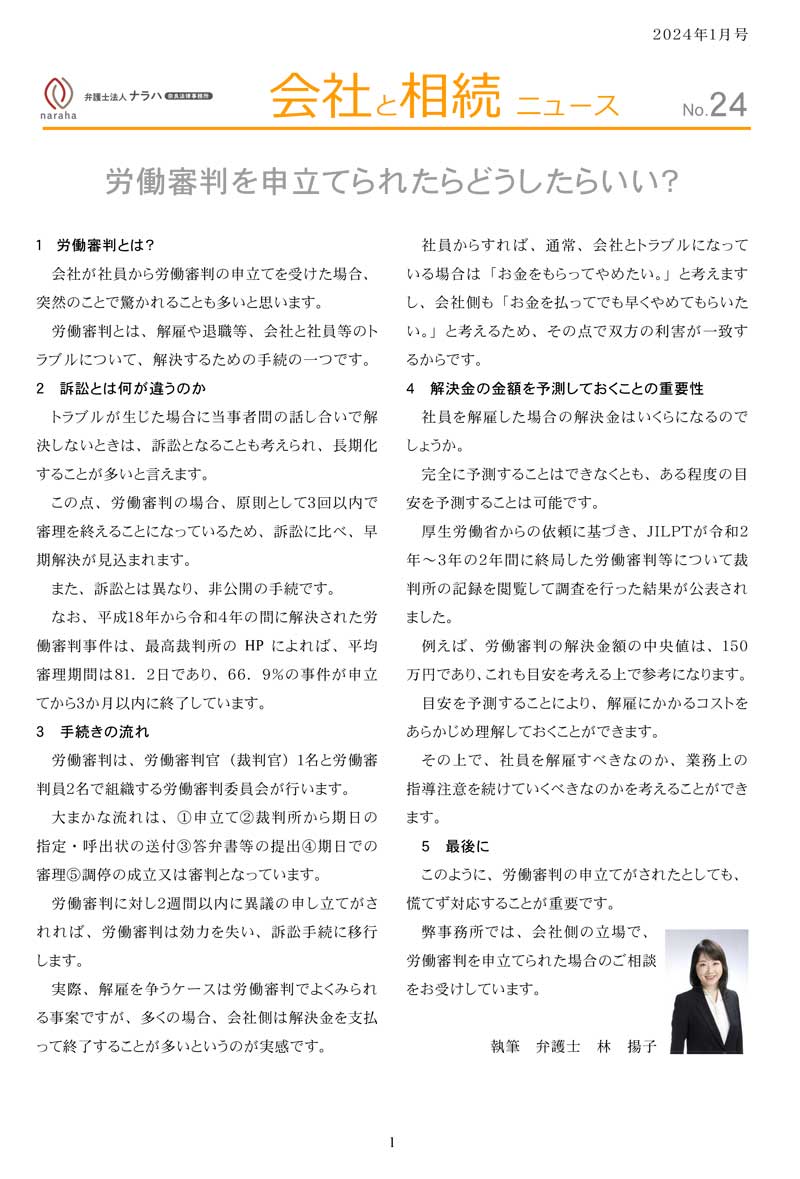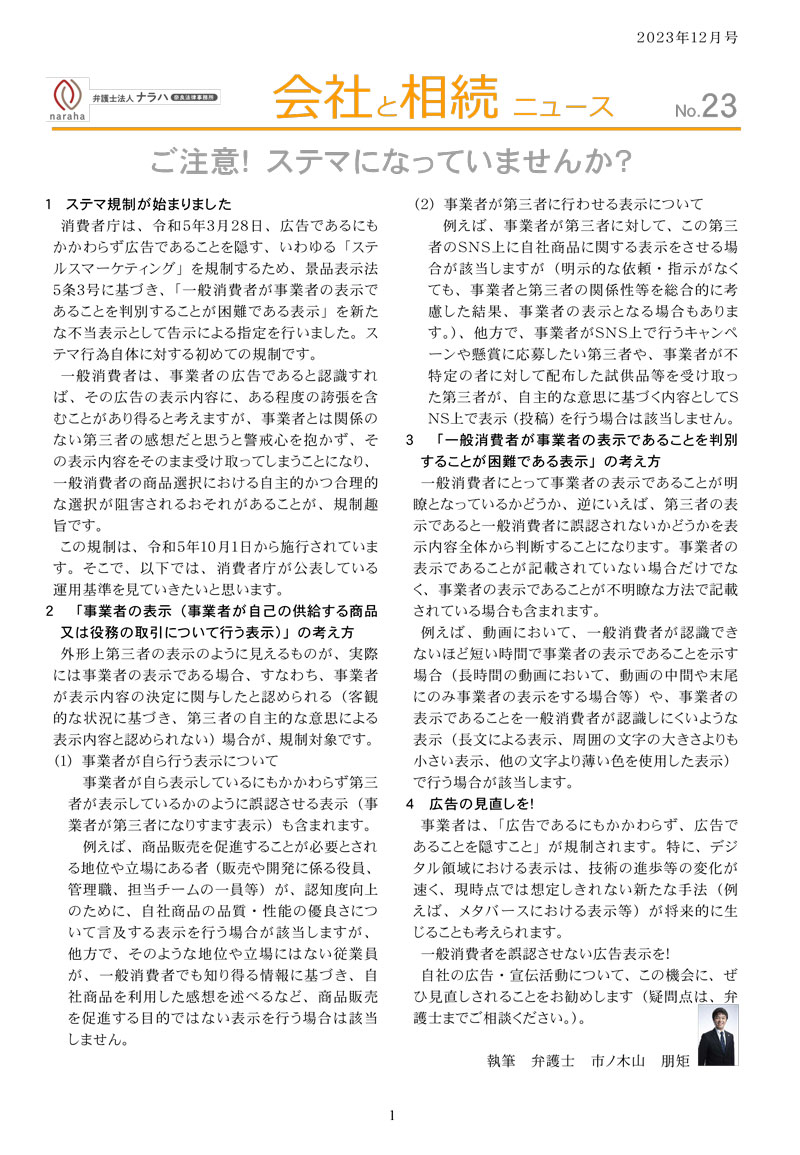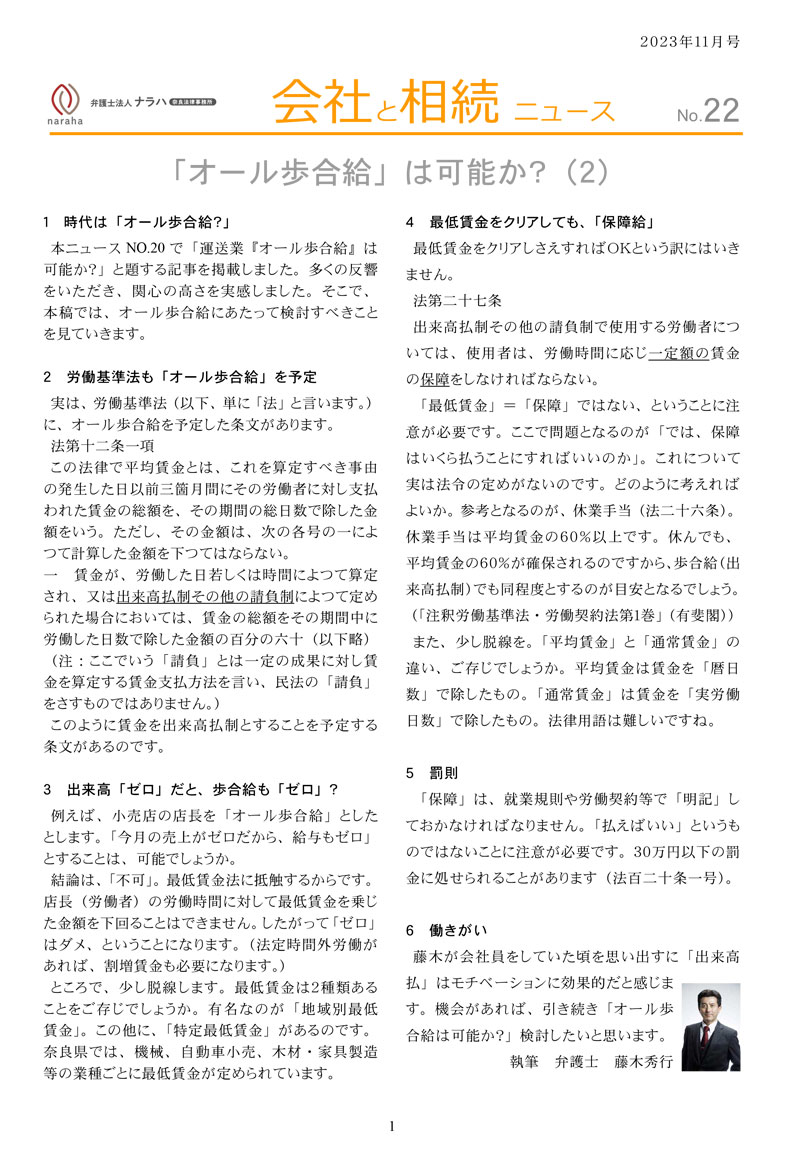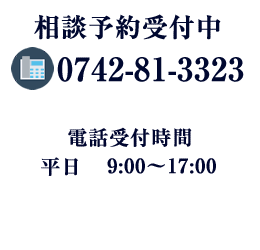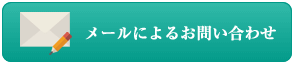労働審判を申立てられたらどうしたらいい?(会社と相続ニュース No.24 2024年1月号)
- 2023年12月27日
- 会社と相続ニュースバックナンバー
労働審判を申立てられたらどうしたらいい?
1 労働審判とは?
会社が社員から労働審判の申立てを受けた場合、突然のことで驚かれることも多いと思います。
労働審判とは、解雇や退職等、会社と社員等のトラブルについて、解決するための手続の一つです。
2 訴訟とは何が違うのか
トラブルが生じた場合に当事者間の話し合いで解決しないときは、訴訟となることも考えられ、長期化することが多いと言えます。
この点、労働審判の場合、原則として3回以内で審理を終えることになっているため、訴訟に比べ、早期解決が見込まれます。
また、訴訟とは異なり、非公開の手続です。
なお、平成18年から令和4年の間に解決された労働審判事件は、最高裁判所のHP によれば、平均審理期間は81.2日であり、66.9%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。
3 手続きの流れ
労働審判は、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行います。
大まかな流れは、①申立て②裁判所から期日の指定・呼出状の送付③答弁書等の提出④期日での審理⑤調停の成立又は審判となっています。
労働審判に対し2週間以内に異議の申し立てがされれば、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行します。
実際、解雇を争うケースは労働審判でよくみられる事案ですが、多くの場合、会社側は解決金を支払って終了することが多いというのが実感です。
社員からすれば、通常、会社とトラブルになっている場合は「お金をもらってやめたい。」と考えますし、会社側も「お金を払ってでも早くやめてもらいたい。」と考えるため、その点で双方の利害が一致するからです。
4 解決金の金額を予測しておくことの重要性
社員を解雇した場合の解決金はいくらになるのでしょうか。
完全に予測することはできなくとも、ある程度の目安を予測することは可能です。
厚生労働省からの依頼に基づき、JILPTが令和2年~3年の2年間に終局した労働審判等について裁判所の記録を閲覧して調査を行った結果が公表されました。
例えば、労働審判の解決金額の中央値は、150万円であり、これも目安を考える上で参考になります。
目安を予測することにより、解雇にかかるコストをあらかじめ理解しておくことができます。
その上で、社員を解雇すべきなのか、業務上の指導注意を続けていくべきなのかを考えることができます。
5 最後に
このように、労働審判の申立てがされたとしても、慌てず対応することが重要です。
弊事務所では、会社側の立場で、労働審判を申立てられた場合のご相談をお受けしています。
【ナラハQ&Aコーナー】マイホーム購入資金は戻ってくる?
Q
娘夫婦が離婚の話し合いをしているようです。娘夫婦の自宅購入資金を一部援助しているのですが、このお金は戻ってきますか。
A
自宅購入資金について、貸したのではなく、援助したということであれば、贈与になりますので、このお金が戻ってくるということはありません。
もっとも、離婚に伴う財産分与で、娘夫婦の自宅を売却して清算する場合、娘夫婦の間でどのように分配されることになるのかは、事案にもよりますので、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
~やってみて、やめたら、いいんだよね~
今、やっていることに、幸せを感じていますか? 藤木は、高校生の頃、オーケストラの指揮者になりたかった。そこで、阪大で阪大オーケストラに入部。しかし、オケをやってみて、指揮者の才能はないことを痛感し、断念。次は哲学者を目指し、哲学科を専攻。しかし、教授や院生が難解な哲学概念を、肌に密着として、日常的概念として語り合う姿に、自らの才能のなさを知り、断念。卒業して一般企業に就職することにしました。
就活の結果、酒造メーカーから内定を頂いたときのことです。当時、藤木は音楽を豊嶋先生という指揮者に教わっていました。豊嶋先生に内定を報告。社会に出る不安から「会社が合わなかったら、どうしよう」と口にしました。一般的な人だったら「大丈夫だよ。なんとかなるよ」とでも言うのでしょうか。ところが、この豊嶋先生はいとも軽やかに、こう、言ったのです。「だったら、やめたら、いいんだよね」。ことばの響きが自然そのもの。「そりゃ、そっか」。藤木は、突如、視野が広がる経験をしたのです。今、藤木は、弁護士をやっています。弁護士をやっているのは、藤木的には、指揮者を目指していたから。今でも、豊嶋先生にお会いし、原点を忘れずにいます。この点、もしかしたら、この仕事、向いていないんじゃないかな、という方、いるかもしれませんね。「やってみて」、合わなかったら、「やめたら、いいんだよね」。