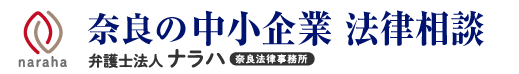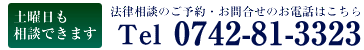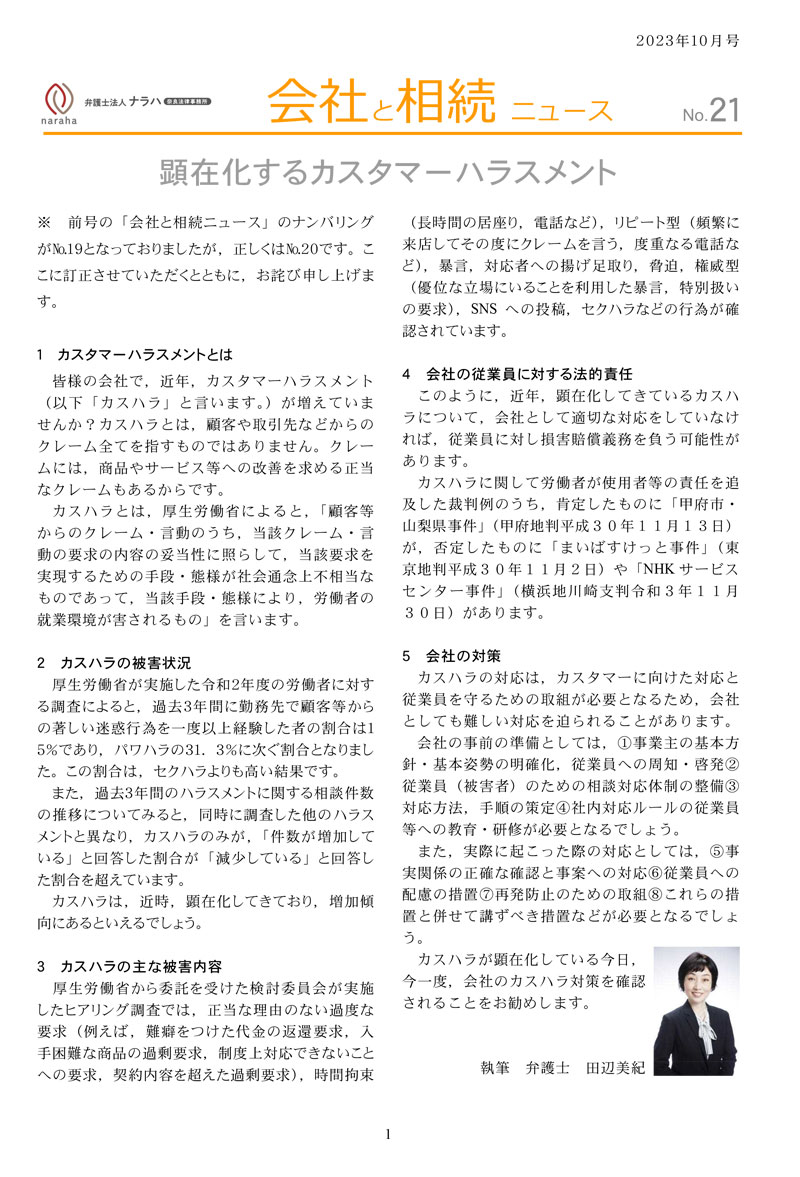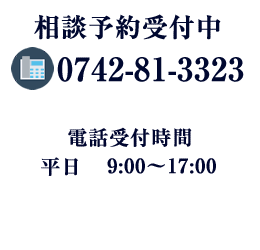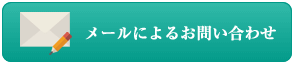顕在化するカスタマーハラスメント
1 カスタマーハラスメントとは
皆様の会社で、近年、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」と言います。)が増えていませんか?カスハラとは、顧客や取引先などからのクレーム全てを指すものではありません。クレームには、商品やサービス等への改善を求める正当なクレームもあるからです。
カスハラとは、厚生労働省によると、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」を言います。
2 カスハラの被害状況
厚生労働省が実施した令和2年度の労働者に対する調査によると、過去3年間に勤務先で顧客等からの著しい迷惑行為を一度以上経験した者の割合は15%であり、パワハラの31.3%に次ぐ割合となりました。この割合は、セクハラよりも高い結果です。
また、過去3年間のハラスメントに関する相談件数の推移についてみると、同時に調査した他のハラスメントと異なり、カスハラのみが、「件数が増加している」と回答した割合が「減少している」と回答した割合を超えています。
カスハラは、近時、顕在化してきており、増加傾向にあるといえるでしょう。
3 カスハラの主な被害内容
厚生労働省から委託を受けた検討委員会が実施したヒアリング調査では、正当な理由のない過度な要求(例えば、難癖をつけた代金の返還要求、入手困難な商品の過剰要求、制度上対応できないことへの要求、契約内容を超えた過剰要求)、時間拘束(長時間の居座り、電話など)、リピート型(頻繁に来店してその度にクレームを言う、度重なる電話など)、暴言、対応者への揚げ足取り、脅迫、権威型(優位な立場にいることを利用した暴言、特別扱いの要求)、SNS への投稿、セクハラなどの行為が確認されています。
4 会社の従業員に対する法的責任
このように、近年、顕在化してきているカスハラについて、会社として適切な対応をしていなければ、従業員に対し損害賠償義務を負う可能性があります。
カスハラに関して労働者が使用者等の責任を追及した裁判例のうち、肯定したものに「甲府市・山梨県事件」(甲府地判平成30年11月13日)が、否定したものに「まいばすけっと事件」(東京地判平成30年11月2日)や「NHK サービスセンター事件」(横浜地川崎支判令和3年11月30日)があります。
5 会社の対策
カスハラの対応は、カスタマーに向けた対応と従業員を守るための取組が必要となるため、会社としても難しい対応を迫られることがあります。
会社の事前の準備としては、①事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発②従業員(被害者)のための相談対応体制の整備③対応方法、手順の策定④社内対応ルールの従業員等への教育・研修が必要となるでしょう。
また、実際に起こった際の対応としては、⑤事実関係の正確な確認と事案への対応⑥従業員への配慮の措置⑦再発防止のための取組⑧これらの措置と併せて講ずべき措置などが必要となるでしょう。
カスハラが顕在化している今日、今一度、会社のカスハラ対策を確認されることをお勧めします。
執筆:弁護士 田辺美紀
【ナラハQ&Aコーナー】元夫が子どもに会わせてくれない
Q
夫と離婚するに当たり、経済的な事情から、夫が子どもの親権者となりました。その後、夫が子どもに会わせてくれません。どうしたら良いでしょうか。
A
家庭裁判所に面会交流調停の申立をすれば、家庭裁判所の助言を得ながら、話し合いをすることができます。場合によっては、専門性を持つ家庭裁判所調査官が調停に入り、子どもの意向を調査するなどして、より良い解決を目指し、話し合いを進める手助けをしてくれます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
回答:弁護士 有年孝将
■ コラム ■
~休日の私と子ども~
私はたぶん超インドア派です。
休日はできれば1日中寝ていたいし、外に出る気になかなかなれません。
しかし、2歳8カ月の子どもがそれを許してくれず、ボール遊びをしたり、歌を歌ったり、家じゅうを走り回ったりするので、寝て過ごす休日は夢のまた夢です。
最近では、おもちゃの子供用携帯電話がお気に入りで、床に寝転がりながら、「ハイ、ハイ」「疲れちゃったわ~」などと喋っており、自分そっくりな姿がそこにありました。
少しずつ自分に似てきている様子が可愛くもあり、なんとなく恐ろしい気もします。
「かあちゃんはいつも家でごろごろしている!」と外で言われないよう、次の休日は外に出かけようと思いました。
執筆:弁護士 林揚子