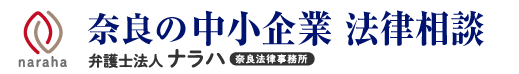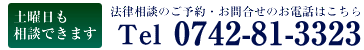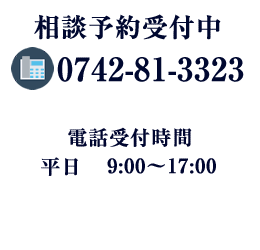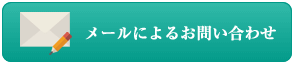Q 弊社は、店舗の商品を、通販サイトでも販売しています。今回問題となったのは、オフィス用の特殊な観葉植物の写真です。その写真は、弊社のオフィス内で、弊社スタッフが撮影したもので、商品のコンセプトや特徴などが伝わるように、様々な工夫をして独特の画像となっています。
先月、他社のホームページの中で、たくさんのイメージ写真に混じって、弊社の写真が使われていることが分かりました。弊社の総務担当者が電話で問い合わせたところ、「『引用』であるため違法ではない」旨の回答がありました。たしかに、ホームページの隅に、引用元として弊社の名前が記載されています。それ以外に、写真の説明や写真に対するコメントなどはありません。
弊社としては、他社に無断で利用されるのは避けたいと考えています。どのように対応すればいいでしょうか。
A よくある誤解の一つです。結論からいえば、この事案では「引用」の要件は満たしておらず、貴社の著作権は侵害されていると考えられます。本格的に争うとなれば、「警告書」を出したうえ、交渉を始めることになると思います。
まず、貴社の写真は、貴社が工夫して撮影されたものということですので、創作的に表現したものとして、「著作物」にあたる可能性は高いといえます。
次に、他社が主張する「引用」の要件を満たすかを検討します。
この点、著作権法上認められる「引用」といえるためには、そもそも「引用の必要性」が求められます。その必要性とは、報道、批評、研究などの正当な理由をいいます。
ご相談の事例では、他社のホームページのイメージ写真の中に混じっていたもので、写真についてのコメントもない、ということです。そうすると、単に写真を利用しているだけ、ということになります。そのような事案においては、そもそも引用の必要性がないというべきと考えます。そのため、著作権法で許される「引用」には該当しないものと考えられます。
ケースバイケースの判断が求められることが多いですので、詳しくは弁護士等の専門家にご相談ください。