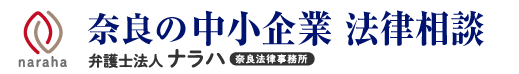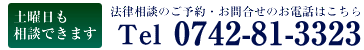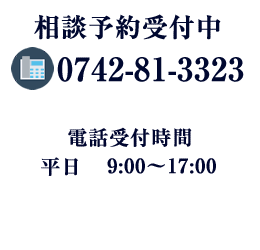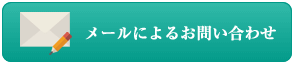1 改革の目標―「働き方を自由に選択できる」社会を目指す
毎日のようにマスコミに登場するキーワード、「働き方改革」。今さら人に聞けない「働き方改革」の概要を分かり易くお話します。
ここでいう「働き方」とは、一言でいうと、「雇用の種類」です。正社員、パート、有期契約などの種類です。その種類を「働く人が自由に選択できる」ようにするというのが、「働き方改革」です。
改革の目的は、「一億総活躍社会」の実現です。あらゆる人が、自分自身の状況に応じた働き方を選択できるようになると、ほぼ全国民、いわば一億人が活躍する社会になる、という政策です。イメージは伝わりましたでしょうか。頑張って働くとか、リラックスして働くという意味での、「働き方」の改革ではないのです。
2 改革点の2つのポイント
では、具体的に、どんな規制が新たに設けられたのでしょか。
(1)労働時間の規制の見直し
まず、大きなポイントが労働時間の規制です。①残業時間の上限の規制の創設、②勤務間インターバル制度の導入、③年間5日間の有給休暇の取得義務化、④残業代の割増率の増加、⑤労働時間の状況把握の義務化、⑥フレックスタイム制の制度拡充、⑦高度プロフェッショナル制度の新設といった7点にわたって、見直しがなされました。
これらは、いずれも、長時間労働をなくための制度改革です。ワーク・ライフ・バランスを維持することも目的の一つですが、「一億総活躍社会の実現」という観点からみると、働く人が自分の事情に応じて、仕事を選び易くするため、労働時間を制限するという仕組みです。
なお、医療機関の方々は、ご存じのように、「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書(平成31年3月28日)がまとめられました。これにより、医師の時間外労働については、2024年以降の上限は年間960時間、条件付きですが地域医療の確保や研修期間の場合は年間1860時間となる見通しです。
(2)非正規社員の公正な待遇
次に、会社の中での正社員と非正規社員の間の「不合理な待遇の差」が禁止されます。あらゆる人が自分に応じた「働き方を選択できる」ようにするためには、パートや有期契約など、どのような雇用の種類を選択しても、待遇に納得して働き続けられることが大切という考え方から、規制が強化されました。
具体的な考え方については、「同一労働同一賃金ガイドライン」が厚生労働省ホームページで示されており、参考になります。
<関連判例―ハマキョウレックス・長澤運輸事件>
昨年(2018年)の6月1日、最高裁で、同一労働同一賃金に関する著名な判決が出されました。いずれも有期雇用の労働者が原告となったケースでした。
1つ目は、「各種手当」の有無という待遇差が問題になりました。「無事故手当」「家族手当」といった諸手当について、正規社員については支給し、有期雇用労働者に支払われなかったという事案でした(いわゆるハマキョウレックス事件)。この判決では、当該手当の性質や目的から考えて、雇用期間の定めの有無で差が生じることが合理的か否かという視点から、待遇差の合理性が判断されました。たとえば、「無事故手当」や「通勤手当」は、雇用期間の差は無関係であるため、有期雇用労働者に支給しないことは不合理であると判断されました。これに対し、「住宅手当」については、正社員については転勤があるなど「人材活用の仕組み」が異なることから、正社員にのみ支給しても不合理とはいえないと判断されました。
2つ目は、定年後再雇用の有期雇用契約者が原告でした(いわゆる長澤運輸事件)。判決では、ハマキョウレックスの判例に沿いつつ、定年後の再雇用の場合は、長期雇用が想定されていないことが重視され、結論としては、会社の賃金体系の合理性が肯定されました。
今後、この判例や厚生労働省のガイドラインを参考にしつつ、各種手当の趣旨の確認と、支給条件の検討・見直しが各企業様において必要になると思われます。
(3)関連する施策
①フレックスタイム制の拡充
フレックスタイム制とは、分かり易くいうと、労働者が始業・終業時間を選べる制度です。一日の労働時間帯が、必ず勤務すべき「コアタイム」と、選択可能な「フレキシブルタイム」、「休憩時間」に分かれます。総労働時間を清算期間(かつては最大1か月)で決めておき、その中で労働時間を清算することとなっていましたが、今回の法改正により、清算期間が最大3か月となりました。
これにより、労働者側としても使いやすくなりますが、使用者側としても、繁忙期のある業種などではメリットが大きく、今後利用が広がると思われます。
②患者さんとのトラブル
患者さんとのトラブルが発生した場合は、医療機関の責任の範囲を確認したうえで、迅速かつ円満な解決となるようアドバイスをいたします。
万一、医療機関側から患者さんに、診療費等の未払を請求するとなった場合、患者さんが帰国した後であれば、任意の履行はほぼ不可能であり、訴訟を検討することになりますが、これはいわゆる国際訴訟となってしまいます。たとえば、中国と日本では、いずれの国で裁判したとしても、その裁判所の判決は、もう一方の国では強制執行できません。このことからもトラブルの「予防」が極めて大切ですが、万一の場合は、迅速な現実的解決の方法を弁護士が助言いたします。
(3)弁護士の活用方法―医療コーディネーター、旅行会社側の立場
①医療機関との基本契約の締結
医療機関との間で、「業務委託基本契約」や「販売代理店契約」を結ぶことになりますが、その契約交渉は慎重に進める必要があります。医療コーディネーターや旅行会社の立場を超えたような不合理な責任を負わされないのか、貴社の強みや特徴が活かせるような役割分担になっているのかを検討する必要があります。契約条項を弁護士が分析し、修正案と交渉方法をアドバイスいたします。
②兼業・副業について
従来から注目されていましたが、一連の改革と関係し、厚生労働省から「兼業・副業の促進に関するガイドライン」が出されました。兼業とは、ある会社で正社員として勤務しつつ、アルバイトをしたり、自営で仕事をするという意味です。
現状では、大部分の企業が職務専念義務や競業避止義務の関係から、禁止しているのが実情ですが、政府としては、キャリアの多様性の観点から、促進する姿勢を明らかにしました。報道によると、解禁の方向性を明らかにしている企業もあります。
兼業・副業を認める場合、使用者として気にかけたいのは、労働時間の管理です。副業であっても、労働時間を管理する義務があると解釈されているため、例えば、適正な自己申告を受ける制度を作る必要があると考えます。
③在宅勤務・テレワーク
働き方の多様性と関係して、在宅勤務・テレワークについて、少しお話します。ネット環境さえあれば、事業所に集まらなくとも業務可能な職種が増えていることを背景として、今後も拡大すると思われます。企業としても、オフィスの削減などのコスト面のメリットや、人材確保のメリットがあり、これに対し、従業員の側では、通勤時間の削減、ライフスタイルに合わせた勤務が実現しやすくなるというメリットがあります。
企業側の法律面での一番の課題は、労働時間の管理です。単なる在宅勤務であれば、必ずしも「みなし労働時間制」が利用できるとは限りません。労働時間管理や残業命令などの指示が甘いと、不意に、残業代請求を受けるというリスクもありえます。導入には、適正な準備が必要不可欠であると思われます。
厚生労働省からは、「在宅勤務ガイドライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」が出ており、参考になります。
3 現場での対応
(1)「時間」に神経質に
従業員さんは、今までにも増して、労働時間を意識するようになると予想されます。これは、改革の目的なのかもしれませんが、仕事観が変化すると思われます。従業員さんたちは、仕事が完成したかどうかよりも、「労働時間」を基準に行動する風潮になるでしょう。「時間が来れば、仕事が終わっていなくても帰る」という行動は、かつては無責任として批判の対象だったかもしれませんが、今は、その態度こそ法律が目指している姿ともいえます。むしろ、そのような労働環境を前提に、仕事の仕組みを改革する必要があると思われます。
(2)有期社員やパート社員の待遇差の説明
求職者はもちろん、勤務中の従業員さんたちも、「待遇差」を非常に意識するようになるでしょう。たとえば、かつては、「パートだから」という一言だけで、待遇差の説明が済まされてきた例があったかもしれません。しかし、今回の改正により、規定の整備と説明を求められた場合の説明義務が法律で定められました。
4 弁護士の活用方法
このような大きな改革であり、新たに気配りをしておくポイントは多数あります。トラブル予防の観点はもちろんですが、むしろ、筆者の顧問業務の現場の感覚からしますと、人事制度やキャリア・パスが、適正で明確になっていることが、優秀な人材の確保・定着に不可欠になっていると思います。
法律顧問として、たとえば、弁護士は次のようなお手伝いをすることができます。
①従業員への説明の準備、補佐
権利意識の高い従業員さんの中には、早速、労働時間や待遇差について、質問や疑問を投げかけてくることがあります。法律が施行された以上、「働き方改革」に対応していない状況を放置するのは、職場の士気にかかわります。
弁護士が、経営者様の立場から、従業員さんへの説明の準備、面談のサポートなどをいたします。
②規定の整備、改善点のアドバイス
御社の状況を把握させていただいたうえで、就業規則や社内諸規定の修正・整備の要否について、アドバイスさせていただきます。
御社の顧問の社会保険労務士の先生と連携して、御社に最適な対応策をアドバイスいたします。