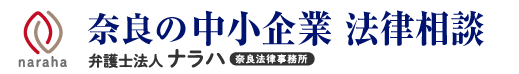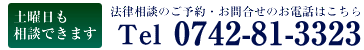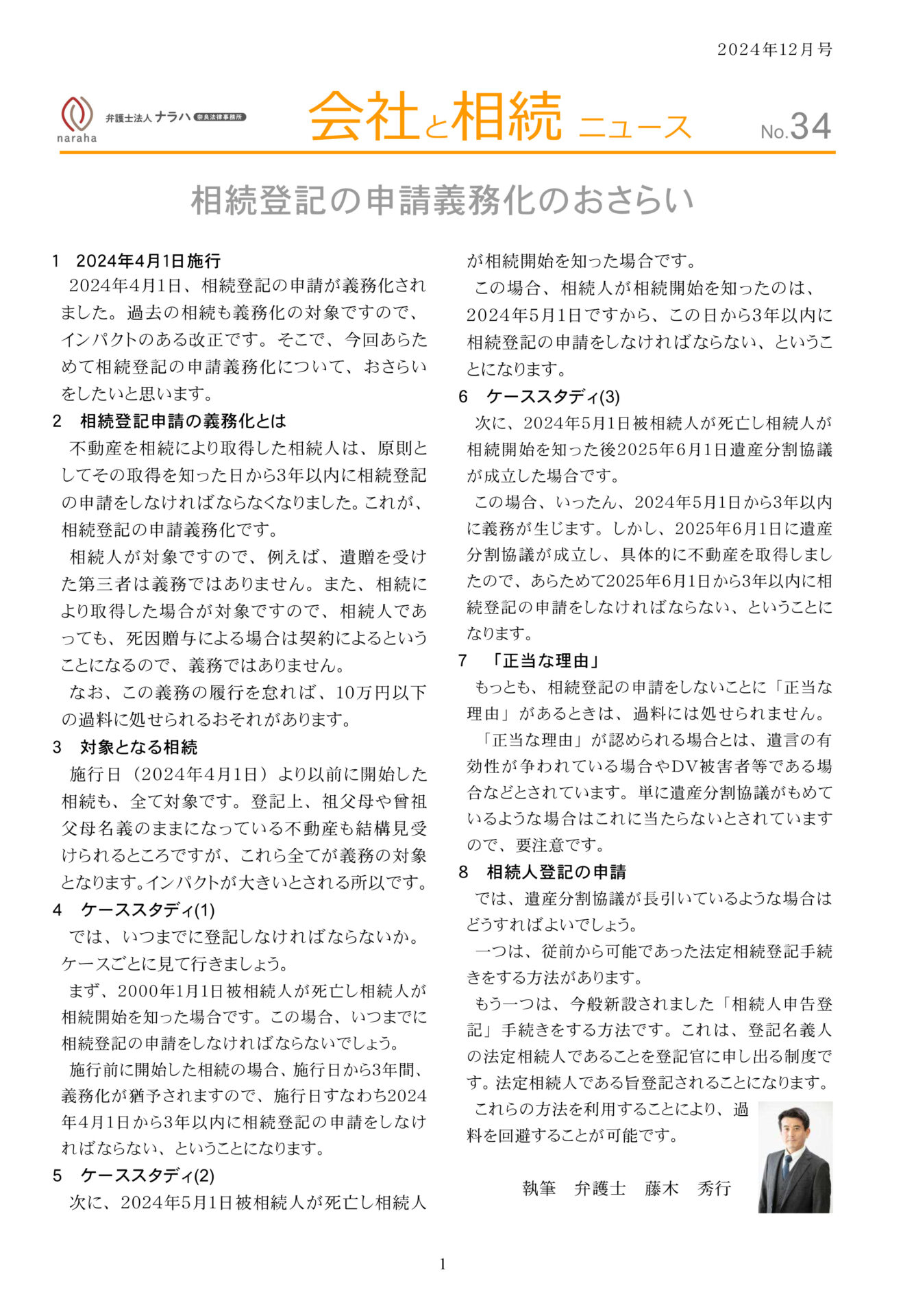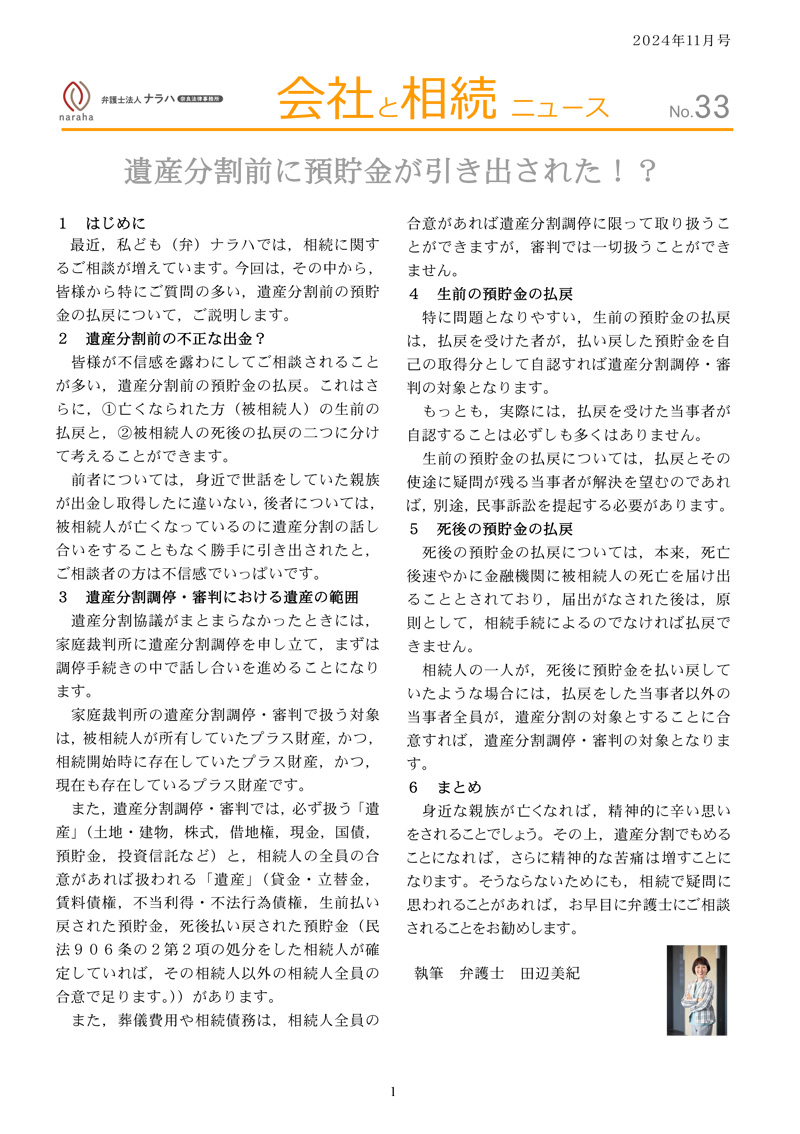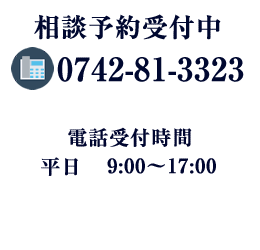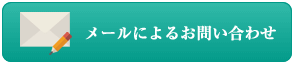相続登記の申請義務化のおさらい
1 2024年4月1日施行
2024年4月1日、相続登記の申請が義務化されました。過去の相続も義務化の対象ですので、インパクトのある改正です。そこで、今回あらためて相続登記の申請義務化について、おさらいをしたいと思います。
2 相続登記申請の義務化とは
不動産を相続により取得した相続人は、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。これが、相続登記の申請義務化です。
相続人が対象ですので、例えば、遺贈を受けた第三者は義務ではありません。また、相続により取得した場合が対象ですので、相続人であっても、死因贈与による場合は契約によるということになるので、義務ではありません。
なお、この義務の履行を怠れば、10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
3 対象となる相続
施行日(2024年4月1日)より以前に開始した相続も、全て対象です。登記上、祖父母や曾祖父母名義のままになっている不動産も結構見受けられるところですが、これら全てが義務の対象となります。インパクトが大きいとされる所以です。
4 ケーススタディ(1)
では、いつまでに登記しなければならないか。ケースごとに見て行きましょう。
まず、2000年1月1日被相続人が死亡し相続人が相続開始を知った場合です。この場合、いつまに相続登記の申請をしなければならないでしょう。
施行前に開始した相続の場合、施行日から3年間、義務化が猶予されますので、施行日すなわち2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、ということになります。
5 ケーススタディ(2)
次に、2024年5月1日被相続人が死亡し相続人が相続開始を知った場合です。
この場合、相続人が相続開始を知ったのは、2024年5月1日ですから、この日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、ということになります。
6 ケーススタディ(3)
次に、2024年5月1日被相続人が死亡し相続人が相続開始を知った後2025年6月1日遺産分割協議が成立した場合です。
この場合、いったん、2024年5月1日から3年以内に義務が生じます。しかし、2025年6月1日に遺産分割協議が成立し、具体的に不動産を取得しましたので、あらためて2025年6月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、ということになります。
7 「正当な理由」
もっとも、相続登記の申請をしないことに「正当な理由」があるときは、過料には処せられません。
「正当な理由」が認められる場合とは、遺言の有効性が争われている場合やDV被害者等である場合などとされています。単に遺産分割協議がもめているような場合はこれに当たらないとされていますので、要注意です。
8 相続人登記の申請
では、遺産分割協議が長引いているような場合はどうすればよいでしょう。
一つは、従前から可能であった法定相続登記手続きをする方法があります。
もう一つは、今般新設されました「相続人申告登記」手続きをする方法です。これは、登記名義人の法定相続人であることを登記官に申し出る制度です。法定相続人である旨登記されることになります。
これらの方法を利用することにより、過料を回避することが可能です。
執筆:弁護士 藤木秀行
【ナラハQ&Aコーナー】子どもの連れ去り
Q
夫と離婚の話合いをしていたところ、夫が子どもを連れて実家に帰ってしまいました。子どもを連れ戻すにはどうしたらいいでしょうか
A
夫との間で話合いがまとまらない場合、例えば、子の監護者指定・引渡しを求める審判(又は調停)を家庭裁判所に申し立てることが考えられます。審判手続きには数か月、事案によっては1年ほどかかるため、迅速性を求めて、併せて保全処分の申立てを行うことも多くあります。
子どもが連れ去られてしまったら、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
執筆:弁護士 金丸有希
■ コラム ■
~散歩で気分転換~
数日前、少し時間があったので普段はよく電車で移動する近鉄学園前駅から富雄駅の間を歩いてみました。
一駅ですが、外の空気を吸い、ゆっくりと景色を見て歩いているとリラックスでき、学生時代もよく気分転換に京都御所を散歩していたことを思い出しました。
ゆっくり歩いてみると、普段車や電車では見過ごしていたお店や景色をじっくり見ることができ、考え事もでき、思っていた以上にとても充実した時間を過ごせました。
せっかく涼しくなり、良い季節になったので隙間時間を見つけて散歩を続けたいと思います。
執筆:弁護士 林揚子