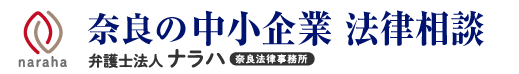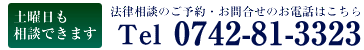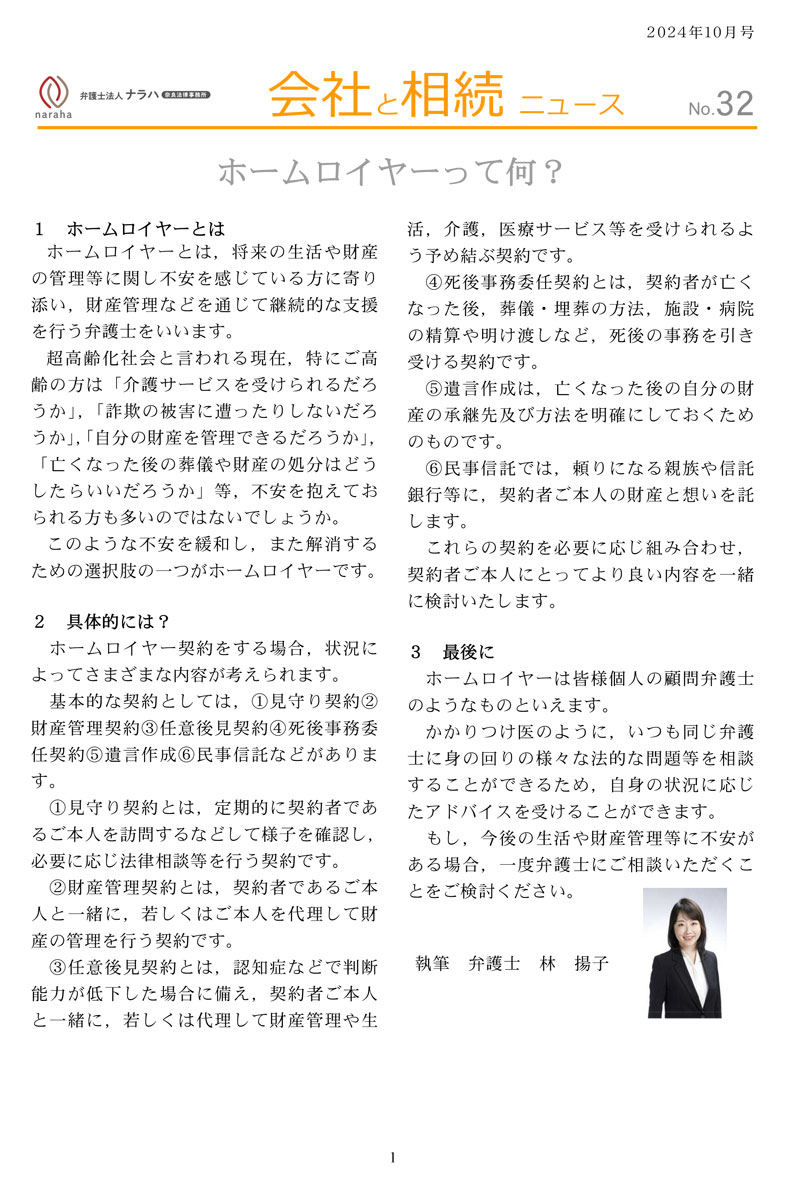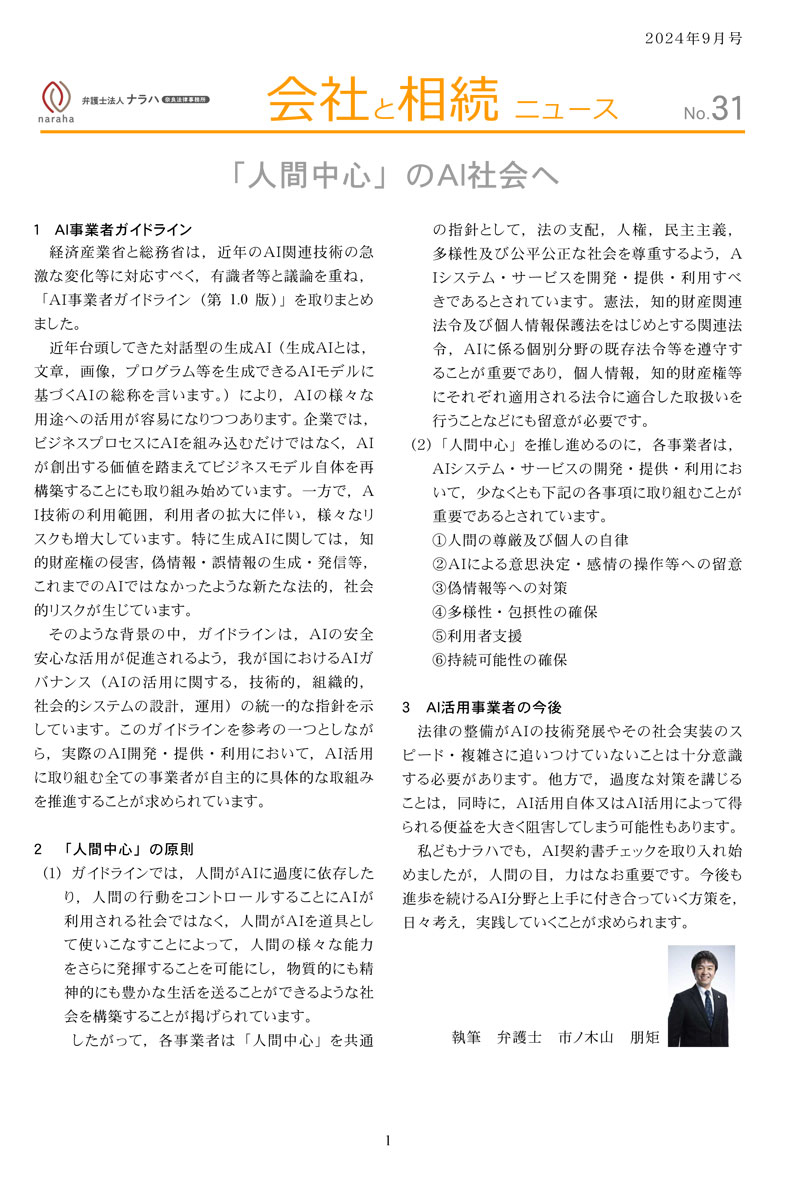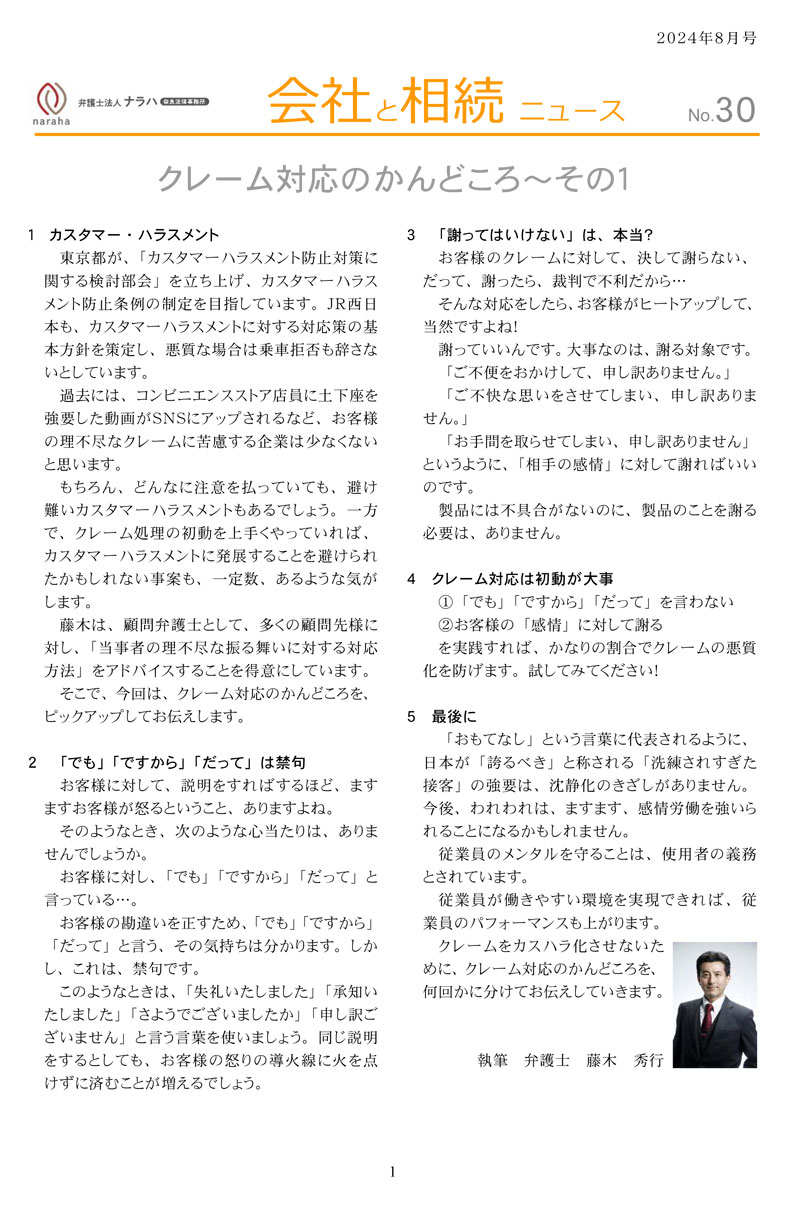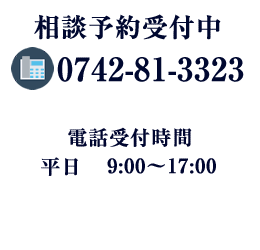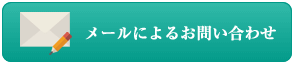ホームロイヤーって何?(会社と相続ニュース No.32 2024年10月号)
- 2024年09月27日
- 会社と相続ニュースバックナンバー
ホームロイヤーって何?
1 ホームロイヤーとは
ホームロイヤーとは、将来の生活や財産の管理等に関し不安を感じている方に寄り添い、財産管理などを通じて継続的な支援を行う弁護士をいいます。
超高齢化社会と言われる現在、特にご高齢の方は「介護サービスを受けられるだろうか」、「詐欺の被害に遭ったりしないだろうか」、「自分の財産を管理できるだろうか」、「亡くなった後の葬儀や財産の処分はどうしたらいいだろうか」等、不安を抱えておられる方も多いのではないでしょうか。
このような不安を緩和し、また解消するための選択肢の一つがホームロイヤーです。
2 具体的には?
ホームロイヤー契約をする場合、状況によってさまざまな内容が考えられます。
基本的な契約としては、①見守り契約②財産管理契約③任意後見契約④死後事務委任契約⑤遺言作成⑥民事信託などがあります。
①見守り契約とは、定期的に契約者であるご本人を訪問するなどして様子を確認し、必要に応じ法律相談等を行う契約です。
②財産管理契約とは、契約者であるご本人と一緒に、若しくはご本人を代理して財産の管理を行う契約です。
③任意後見契約とは、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、契約者ご本人と一緒に、若しくは代理して財産管理や生活、介護、医療サービス等を受けられるよう予め結ぶ契約です。
④死後事務委任契約とは、契約者が亡くなった後、葬儀・埋葬の方法、施設・病院の精算や明け渡しなど、死後の事務を引き受ける契約です。
⑤遺言作成は、亡くなった後の自分の財産の承継先及び方法を明確にしておくためのものです。
⑥民事信託では、頼りになる親族や信託銀行等に、契約者ご本人の財産と想いを託します。
これらの契約を必要に応じ組み合わせ、契約者ご本人にとってより良い内容を一緒に検討いたします。
3 最後に
ホームロイヤーは皆様個人の顧問弁護士のようなものといえます。
かかりつけ医のように、いつも同じ弁護士に身の回りの様々な法的な問題等を相談することができるため、自身の状況に応じたアドバイスを受けることができます。
もし、今後の生活や財産管理等に不安がある場合、一度弁護士にご相談いただくことをご検討ください。
【ナラハQ&Aコーナー】共同親権とは何ですか?
Q
妻と離婚したいと考えています。最近、法改正で、共同親権が導入されたと聞いたのですが、どういうことなのでしょうか?
A
共同親権を導入する改正民法が本年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。現行法は、離婚後の子どもの親権は父又は母のいずれかが単独で持つことになっています。改正法では、単独親権に加え、父と母の双方が親権を持つ共同親権とすることも可能となります。改正法の施行日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で定められます。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
~目指せ奈良マラソン~
今年の6月から、ランニングを始めました。運動不足解消のためです。
せっかくなら、目標を持って頑張りたいと思い、早速、12月に開催される奈良マラソンにもエントリーしました。
しかし、元々、走ることが苦手な私。長い距離を走らねばと思いつつ、苦しくてなかなか続かない…。
せっかく奈良マラソンに出場するのに、完走できないのではないかと危機感を抱くようになりました。現状を打破するため、橿原で開催されるランニングクリニックに参加することにしました。ランニングクリニックでは、講師による座学と実技がありました。その際、「まずは、好きな音楽を1曲聞きながら走る、次の曲では早歩きをする、そして次の曲でまた走る…ということを繰り返していると、走れる距離が自然と伸びていきますよ。無理は禁物。」とお話されていました。私は、目から鱗。「そんな簡単なことから始めればよいのか!」と私の肩から力がすっと抜けていきました。それからは、好きな音楽を聞きながら、楽しくランニングすることができています。自然と、走る距離も伸びてきました。最初は小さくても、一歩一歩やっていくことが大切なのだと改めて実感しました。
奈良マラソン完走に向け(10キロですが)、これからも一歩一歩頑張っていこうと思います。