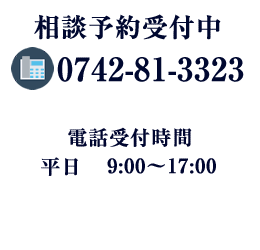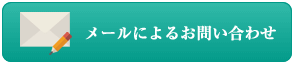1 医療ツーリズムとは…
一般に、患者が自分の治療に相応しい医療機関で受診するため、海外へ渡航することをいいます。最先端の手術を受けるために著名な海外の病院へ向かう例はもちろん、美容形成や人間ドックのために海外へ行く場合も含まれます。(経済産業省は、「医療渡航」という用語を使っています。)
この医療ツーリズムは、世界中で拡大しています。医療ツーリズムの受入れを国家戦略に掲げる国もあります。特に、タイ、マレーシア、韓国、シンガポールは積極的です。はっきりとした統計はないのですが、年間マレーシアは86万人、韓国は30万人という統計があります。
2 日本での受入れの実情
日本の場合、「医療滞在ビザ」を取らずに、「短期滞在ビザ」で通院や人間ドック受診が可能です。そのため、実数は把握されていません。経済産業省作成の資料では、「数千~万人/年」という表現がされています。「医療滞在ビザ」の発給件数は、2016年は1307件でした。2012年と比較して、約6倍の増加となっています。
経済産業省や観光庁は、積極的に、受け入れを推進しています。国際的な認証であるJCI(The Joint Commission International)の認証を取得した国内の医療機関は、平成21年は1施設でしたが、平成30年末の時点で26施設にまで増えました。
今のところ、日本への医療ツーリズムで割合が多いのは、アジア各国からの人間ドックの利用のようです。医療機関の中には、英語や中国語を話す医師、看護師、事務職員を配置している例もあります。
今後、医療ツーリズムが幅広く浸透していくなかで、医療ツーリズムの受入れは、より多くの医療機関の選択肢となっていくでしょう。
3 想定されるリスクと弁護士の活用方法
(1)文化の違い、関係者が多いこと
このように期待の広がる医療ツーリズムですが、どのようなリスクの芽があるでしょうか。まずは、患者さんが日本の医療現場の慣行に慣れていらっしゃらないことから、「誤解」が生じやすいことです。普段の日本語の「同意書」を外国語訳するだけでは大変危険です。患者さんの文化的背景を踏まえてしっかりと対応・フォローができる医療コーディネーターとの連携は大切です。
もっとも、医療コーディネーターや医療通訳など関係者が多いことによる連絡・連携ミスも起こりがちです。
(2)弁護士の活用方法―医療機関側の立場
①医療コーデ―ネーターとの契約
まず、医療コーディネーターとの役割分担をはっきりさせるために、明確な契約を締結する必要があります。具体的な契約交渉となった場合に、契約条項の検討や代替案の提案などのバックアップいたします。さらに、弁護士に交渉の代理人を依頼いただく方法もあります。
②患者さんとのトラブル
患者さんとのトラブルが発生した場合は、医療機関の責任の範囲を確認したうえで、迅速かつ円満な解決となるようアドバイスをいたします。
万一、医療機関側から患者さんに、診療費等の未払を請求するとなった場合、患者さんが帰国した後であれば、任意の履行はほぼ不可能であり、訴訟を検討することになりますが、これはいわゆる国際訴訟となってしまいます。たとえば、中国と日本では、いずれの国で裁判したとしても、その裁判所の判決は、もう一方の国では強制執行できません。このことからもトラブルの「予防」が極めて大切ですが、万一の場合は、迅速な現実的解決の方法を弁護士が助言いたします。
(3)弁護士の活用方法―医療コーディネーター、旅行会社側の立場
①医療機関との基本契約の締結
医療機関との間で、「業務委託基本契約」や「販売代理店契約」を結ぶことになりますが、その契約交渉は慎重に進める必要があります。医療コーディネーターや旅行会社の立場を超えたような不合理な責任を負わされないのか、貴社の強みや特徴が活かせるような役割分担になっているのかを検討する必要があります。契約条項を弁護士が分析し、修正案と交渉方法をアドバイスいたします。
②患者さんとのトラブル
患者さんとの「コーディネート契約」についても、貴社の責任と役割の範囲が明確に規定されているのかを慎重に検討します。診療費の支払いや送金方法、精算方法など、細かく規定すべき事項は多岐にわたります。
患者さんとの間で、キャンセル料の未払や精算のトラブルが発生しないシステムとなるよう、万全を尽くします。契約条項案を弁護士が分析し、修正案と交渉方法をアドバイスいたします。
患者さんからのクレームが発生した場合は、法的責任の有無を判断したうえで、早期解決のためのアドバイスをいたします。代理人としての交渉を弁護士にご依頼いただく方法もあります。
(4)まとめー弁護士によるトラブル予防
トラブルを予防し、万一の発生時に早期解決を図るために、弁護士が出来ることは沢山ございます。日頃から相談できる顧問弁護士はお役に立てるはずです。一度ご相談ください。
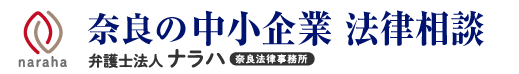


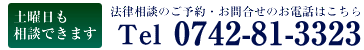

 当事務所一同、より一層励む所存にございますので、新たな10年を歩み始めました当事務所を、今後とも宜しくお願い申し上げます。
当事務所一同、より一層励む所存にございますので、新たな10年を歩み始めました当事務所を、今後とも宜しくお願い申し上げます。