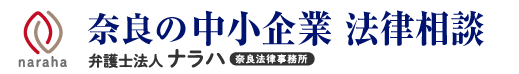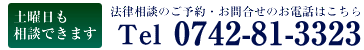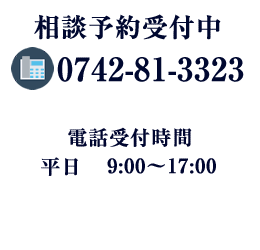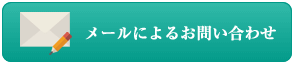Q&A 建物賃貸借の合意解約についての注意点
- 2018年07月17日
- 不動産業・アパート経営, 契約・取引
Q 当社は,貸し店舗をテナントに出していましたが,このたび,賃借人さんとの賃貸借契約を,合意解約することになりました。賃借人さんに対しては,次の年度末である2019年3月末日まで,その貸し店舗の使用を認める予定です。
この合意解約について,合意書を作成する予定ですが,「賃貸借契約の終了日は2019年3月末とする」という表現でよいでしょうか。注意点があれば教えてください。
A ご記載の表現であれば,賃貸借契約は継続することとなります。そのため,2019年3月末日における解約の有効性が争われるリスクがあります。
御社の立場からすれば,「合意解約は本日付けで行い,賃貸借契約は本日終了すること」「2019年3月末日までは,明渡を猶予するにすぎないこと」が明確に分かる条項にすることをお勧めします。