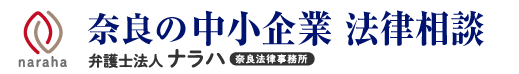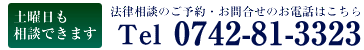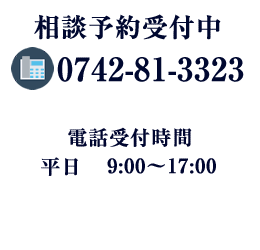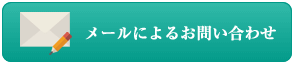Q&A 判断能力が疑わしい利用者さんとの契約
Q 高齢者向けの福祉サービス契約の締結にあたって、利用者となる方の判断能力がはっきりとしない場合、ご家族に代筆してもらう方法を従来していました。しかし、先般、福祉サービスに関し、ご親族からクレームを受けることがあり、その中で、そもそも契約したこと自体がおかしいと指摘を受けました。当初代筆していただいたご家族は、現在は別居しておられ、今回クレームをおっしゃったのは、代筆した方とは別の方です。この出来事から、代筆はリスクが高いことを痛感しました。
今後は、どのようにしていけばよいでしょうか。
A ご本人の判断能力が疑わしい場合は、成年後見人が付いた後に、契約するのが原則となります。ご家族が、判断能力はあると主張され、成年後見制度は必要ないとおっしゃる場合には、主治医の診断書で、判断能力があることを確認し、記録に残すことが大切です。
なお、代筆が有効となりうるのは、ご本人の判断能力がはっきりしているものの、字を書くことができない場合です。このように場合であっても、適正な契約方法であることを説明できるように、その状況を詳しく記録に残すことをお勧めします。